登録支援機関が行政書士法違反にならないための申請業務フロー
この記事の概要
登録支援機関が外国人の在留資格申請を支援する際には、行政書士法と入管法の両方に抵触しない運用が不可欠です。
特に「誰がどの範囲の書類を作成できるか」「誰が入管に対して申請取次を行えるか」という点は誤解されやすく、違反すれば重大なリスクとなります。
本記事では、登録支援機関が適法に在留資格手続を行うための基本ポイントに加え、令和8年1月1日施行の行政書士法改正も踏まえて解説します。
行政書士法の基本と改正内容
現行法
-
行政書士法第1条の2により、官公署に提出する書類を報酬を得て作成できるのは行政書士のみです。
-
登録支援機関の職員が報酬を受け取って入管提出書類を作成すれば違法となります。
改正法(令和8年1月1日施行)
-
条文に**「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」**が追加されます。
-
これにより、従来グレーゾーン的に行われていた「コンサルティング料」「事務手数料」などの名目で書類作成を有償提供することも違法とされる可能性が高いです。
👉 警告ポイント:登録支援機関が「支援料の一部」と称して申請書作成を行うことは、改正後は違法と解釈される可能性が高いです。
入管法の基本:申請取次できる主体
-
入管法上、在留資格申請を本人の代わりに提出できるのは申請取次資格を持つ行政書士等または承認を得た所属機関職員。
-
登録支援機関が承認を得ていれば職員による取次は適法だが、書類作成を有償で行えば行政書士法違反。
-
「誰が作成し、誰が提出するのか」を常に切り分けることが重要。
登録支援機関で起こりやすいリスク(具体例)
1. 別名目での違反
-
申請書作成を「申請サポート費」「コンサルティング料」「事務手数料」と称して請求。
-
実態は入管提出用の申請書類を作成しており、令和8年改正後は名目に関わらず違法。
2. 「サービス一式」に申請代行を含めるケース
-
「外国人採用支援パッケージ」「登録支援フルサービス」などの名称で、生活支援・採用代行と一緒に在留資格申請の書類作成や提出代行を含めて契約。
-
業務の一部が行政書士法の独占業務に該当するため、パッケージ全体がリスクに。
RakuVisaの仕組み:行政書士法違反を回避する設計
RakuVisa for TSKは、コンプライアンスを最優先に設計されています。
-
ユーザー(外国人本人・所属機関・登録支援機関)は入力フォームに入力するだけ
-
入管提出用の正式な申請書類は、行政書士が申請取次の際にシステムで生成
-
「ユーザーが申請書を作成できる」フェーズ自体が存在せず、行政書士法違反のリスクを回避
さらに、
-
入管API連携により常に最新の書式に自動更新
-
申請フローに必ず行政書士が関与する仕組み(外国人本人が自分で申請するセルフプランを除く)
これにより、改正後の行政書士法においても、登録支援機関は安心してRakuVisaを利用できます。
まとめ:改正行政書士法を正しく理解し、適法な運用を
-
行政書士法改正(令和8年施行)により、「コンサル料」などの名目でも有償書類作成は違法化
-
登録支援機関は「支援業務」と「申請業務」を明確に分け、リスクを回避する必要あり
-
RakuVisaはユーザー入力+行政書士取次という設計で、法改正後も安心して利用可能
今後は「少しくらいなら大丈夫だろう」という考えが通用しなくなる可能性が高まります。
登録支援機関は入管法・行政書士法などを見直し、コンプライアンスを最優先に考え、安全な支援フローを確立することが事業継続の条件となることと思われます。

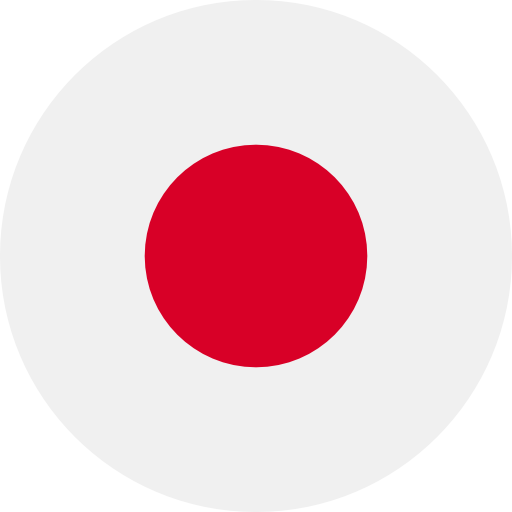 JP
JP